2013年8月26日
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
海外の着物愛好家へ 着物や日本文化を届ける「FURICLE」、9/2(月)にオープン
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
株式会社ソウ(大阪市中央区)は、国内のタンスに眠る8億枚とも言われる着物をはじめ日本の伝統文化に根ざした商品や情報を海外の着物愛好家に届けるサービス『FURICLE』(フリクル)を、2013年9月2日にスタートします。
弊社代表・八木創平は、京都の西陣織工房で生まれ育った背景から、海外での着物振興を模索する活動を行なってきました。Facebook上で外国人を対象とした着物コミュニティを運営するなかで、熱烈な着物愛好家の外国人や、着物に興味があるけれども手に入れる事が難しいと嘆く外国人が多く居る現状を知り、着物に憧れる外国人に、国内にある「タンスの肥やし」8億枚の中古着物を届けるプロジェクトを構想。2013年4月に行われた起業イベント『Startup Weekend Osaka』(http://osaka.startupweekend.org)に出場してチームを結成しビジネスプランを検証、最終プレゼンテーションで優勝を勝ち取りました。その後さらに準備を進め、このたび弊社の事業としてスタートするに至りました。
FURICLEの事業内容は、中古着物を中心とした和文化関連商品の海外向けインターネット販売です。従来のインターネット通販サイトでは満たせていない外国人顧客のニーズに応えるため、FURICLEでは、着物や日本文化に関する高品質な英語コンテンツを提供すると共に、インターネット通話・ビデオ通話・チャット等を積極活用して、外国人顧客との直接対話と能動的コミュニケーションを通じて関係を構築し、提案型営業やコンシェルジュサービスを提供していきます。
また、会員限定の着物プレゼント抽選などの企画による集客や、海外の着物愛好家コミュニティとのコラボレーション、着物に関わるビジネスを行っている現地外国人へのサポートメニューを提供し、海外での着物の普及活動を推進します。
FURICLEは、大阪市のグローバルイノベーション支援拠点「大阪イノベーションハブ」で提供されるLean LaunchPad Osaka等の起業家支援・ベンチャー育成のためのプログラムにも参加しており、今後ベンチャーコミュニティのネットワークを通じた海外での広報活動も展開してゆきます。
FURICLEのコンセプトや詳細については、こちらの日本語サイトをご参照下さい。
http://release.furicle.jp
FURICLEの英語サイトは9月2日にオープンします。(9月1日までは予告サイト。)
http://furicle.jp
なお、英語サイトのオープンに先立ち、クローズド・ベータテストを行っております。詳しくはプレスキットをご参照ください。
【本件に関するお問い合わせ先】
企業名:株式会社ソウ
担当者名:八木創平
Email: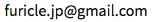
WEB:http://sou-co.jp
住所:大阪市中央区南船場4-10-21
大阪屋エコービル507
電話:06-4708-7909







